
近年、PTA活動に対する保護者の不満や負担感が社会問題として取り上げられるようになりました。
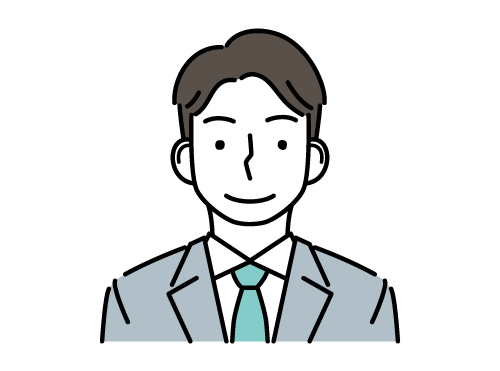
仕事が忙しくて時間が取れないよ
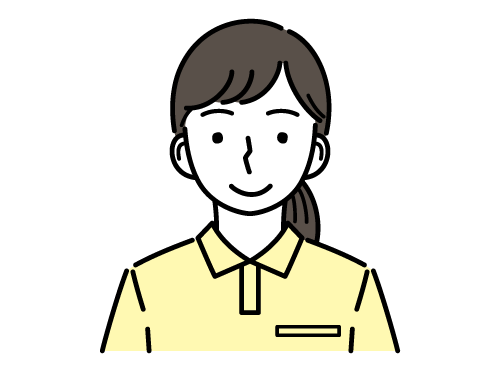
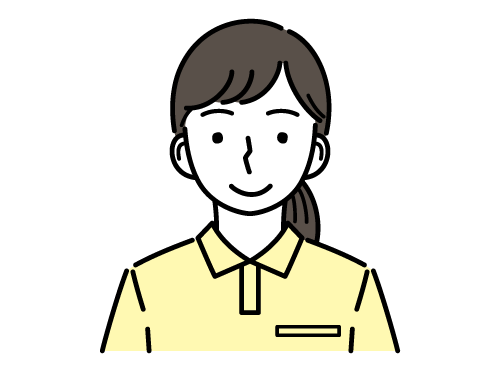
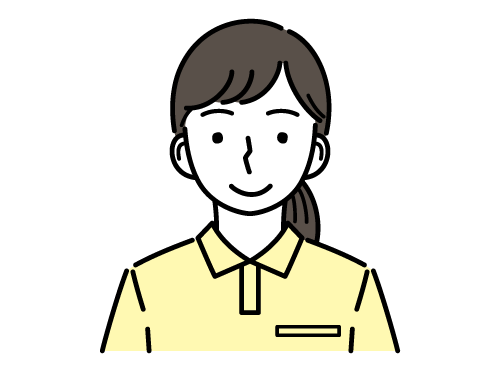
役員になったが何をすればいいのか分からないです
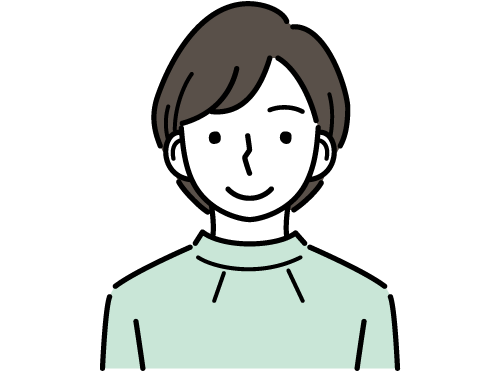
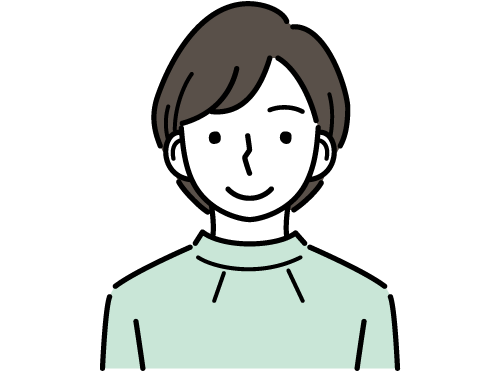
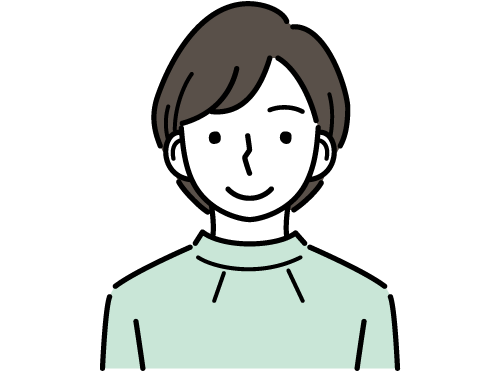
強制加入のような仕組みに納得できないわ
といった声は、多くの学校で聞かれています。こうした状況の中で注目されたのが「ボランティア制」でした。従来のように全員が一律で役割を担うのではなく、希望者が自発的に参加する方式に切り替えれば、活動への心理的ハードルが下がり、より気楽に関われるのではないかという期待があったのです。特に共働き家庭やシングル家庭の増加に伴い、柔軟に関われる仕組みは歓迎され、導入を検討するPTAも増えました。
しかし実際にボランティア制を採用してみると、思うように機能しないケースが多く見られます。担い手不足や責任の所在の曖昧さから活動が停滞したり、結局は一部の熱心な人に負担が集中したりと、当初の理想とは異なる現実に直面するのです。
こうした失敗事例は「自由参加だからこそ難しい」という矛盾を浮き彫りにしており、PTAの組織運営を考える上で避けて通れない課題を示しています。






