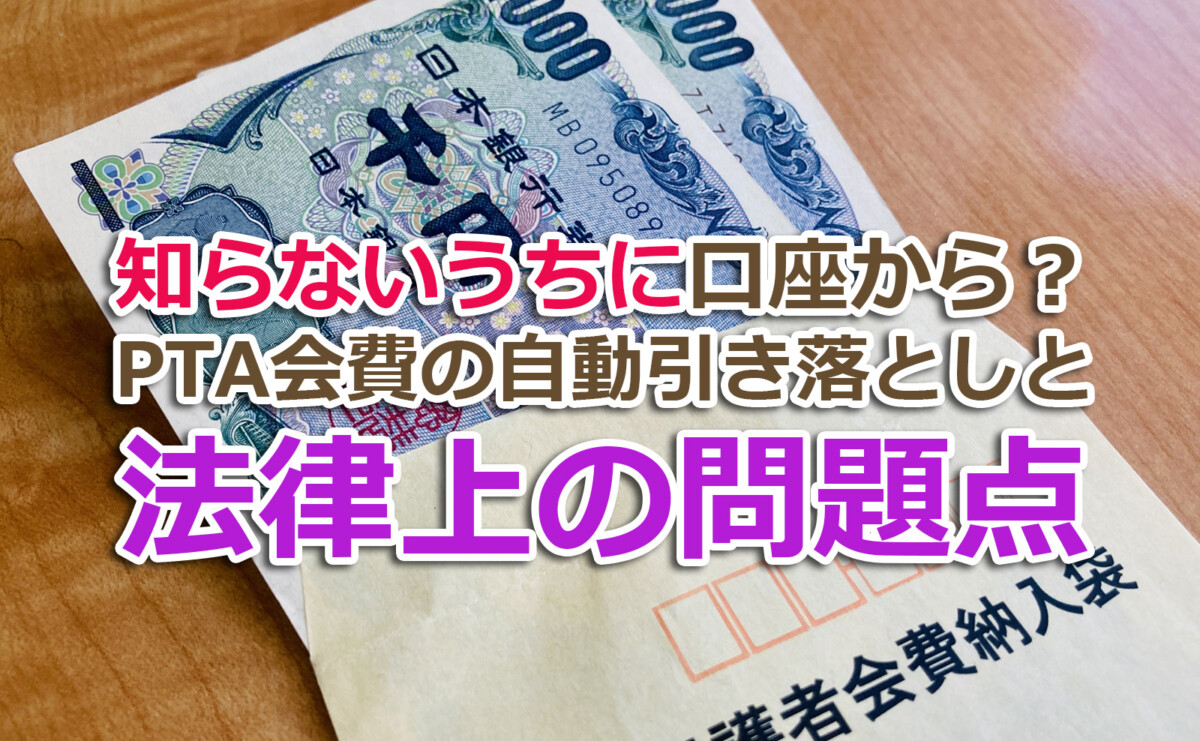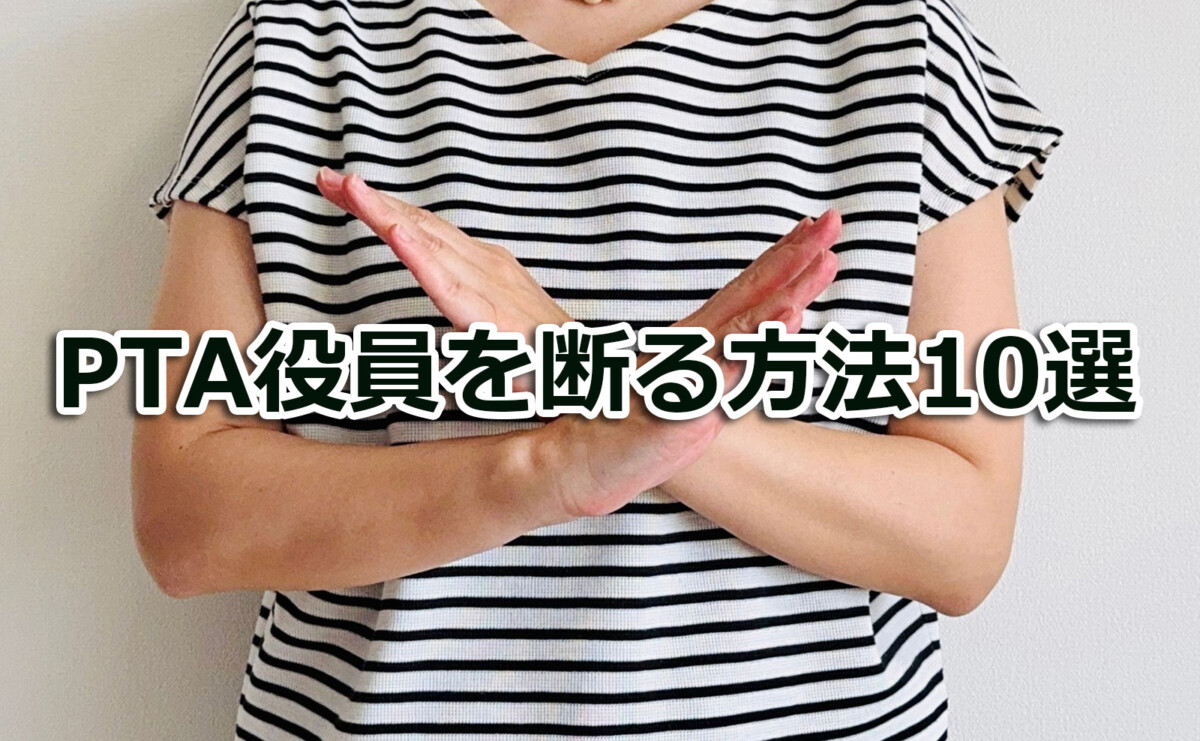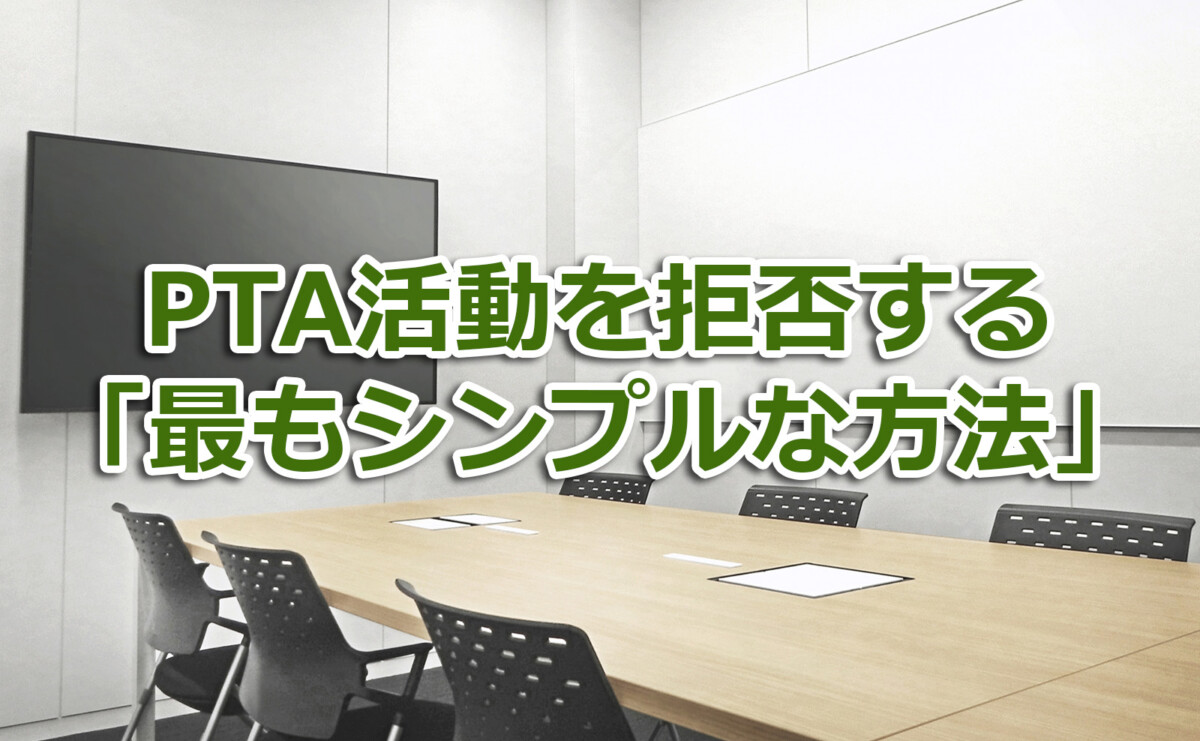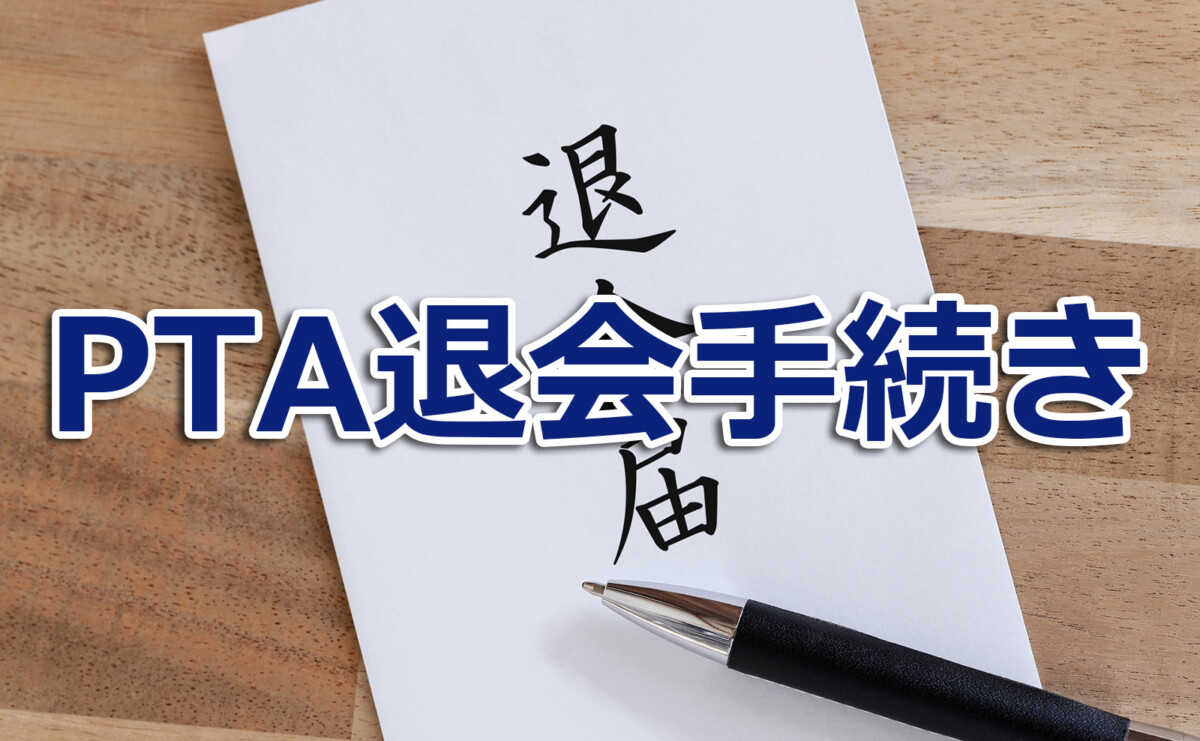近年、SNSや保護者同士の会話のなかで「PTAを退会するなんてずるい」という言葉がたびたび聞かれるようになりました。学校に子どもを通わせていれば、多くの家庭が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。退会した人は「自分だけ楽をしている」と見られがちで、残った人は「負担が増える」と感じてしまう。そこから生まれる摩擦は、親同士の人間関係に大きな影を落とすこともあります。
そもそもPTAは法律上「任意加入の団体」であり、入る・入らないは保護者の自由であるはずです。しかし現実には「入って当たり前」「抜けるなんて非常識」という空気が長く続いてきました。そのため「退会=裏切り」という感覚が残っており、正しい制度理解と現場の意識には大きなギャップがあります。
「ずるい」と言われる背景には、同調圧力や日本的な「みんなで支えるべき」という価値観、さらには役割分担の不均衡があります。一方で、退会を選ぶ人にも仕事や家庭事情、心身の余裕といったやむを得ない事情が存在します。単純に「ずるい」で片づけてしまうのは、本当に正しいのでしょうか。
今回は、なぜPTA退会が「ずるい」と見なされるのか、その言葉の裏にある心理や社会的背景を整理しつつ、これからのPTAとの向き合い方を考えていきます。