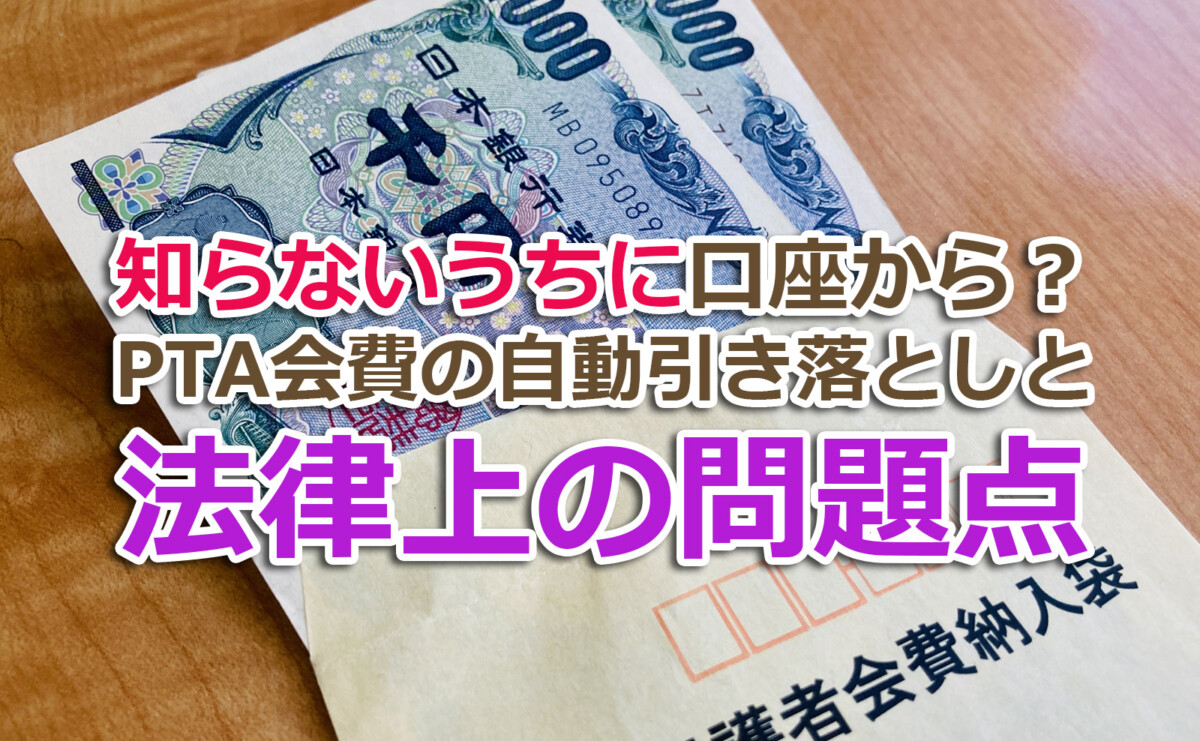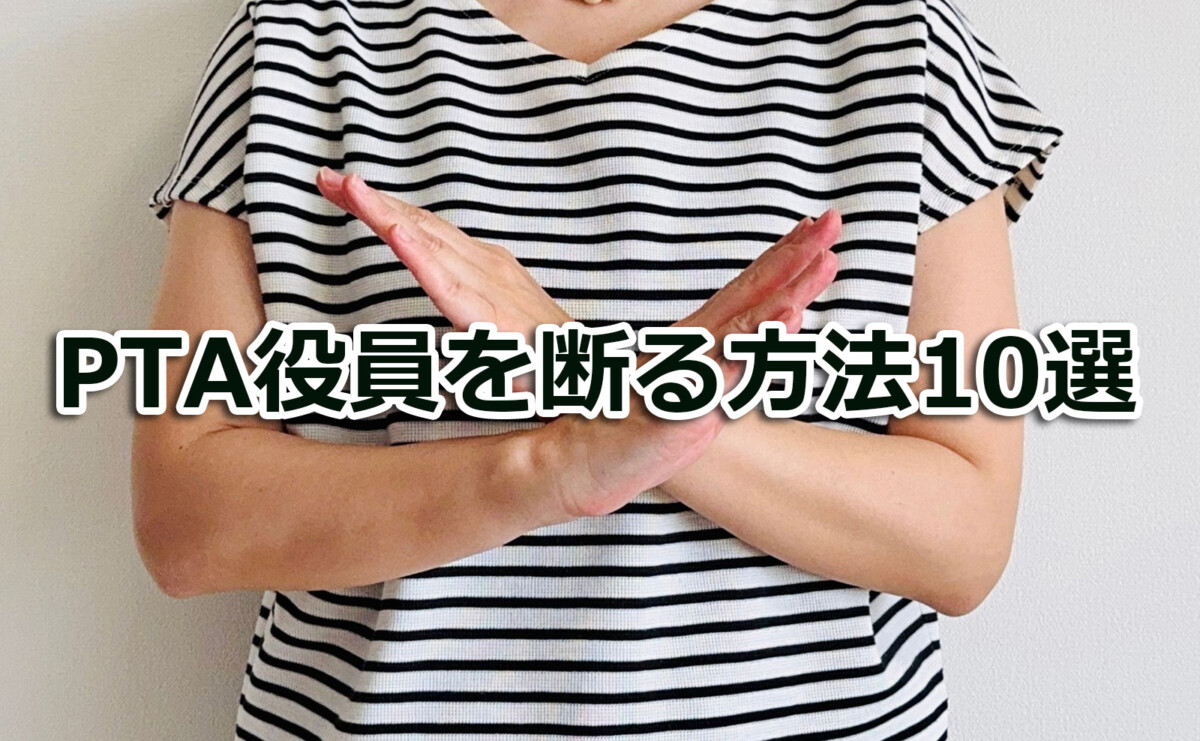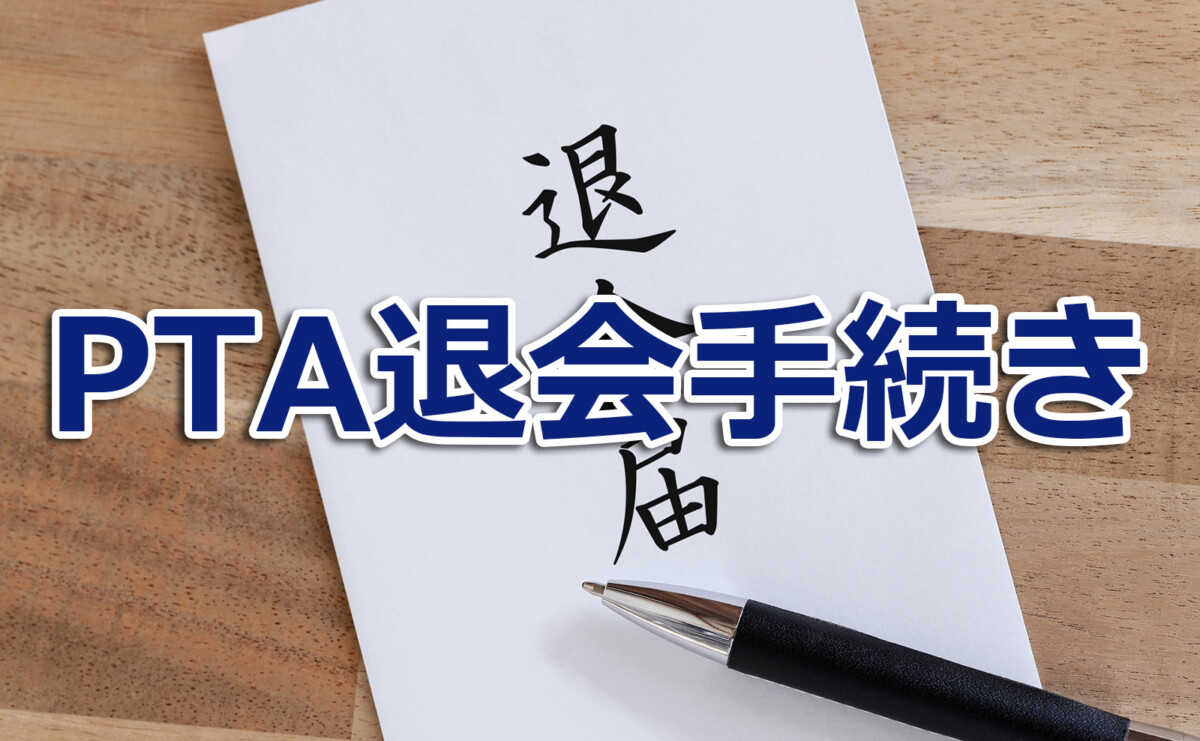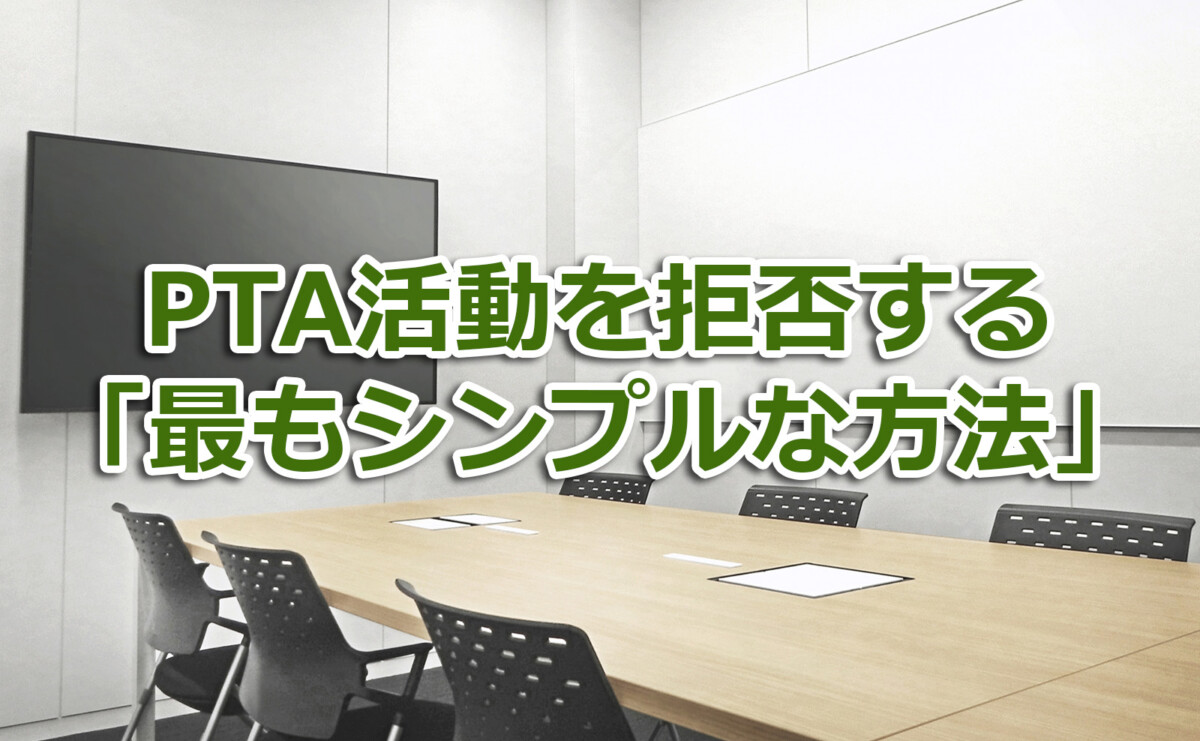
PTAは本来「任意参加」の団体
PTA(Parent-Teacher Association)は、その名のとおり保護者と教職員が協力して子どもたちの成長や学校運営を支える任意団体です。つまり本来は「入りたい人が入り、活動したい人が活動する」仕組みであり、参加はあくまで自由です。しかし、日本では長年にわたり「保護者は全員加入するもの」「母親なら必ず役員を務めるもの」といった固定観念が根強く、事実上の強制参加が常態化してきました。そのため「断る」という発想すら持ちにくく、多くの保護者が半ば義務のように受け止めてきたのです。
ところが近年、共働き家庭の増加やシングル世帯の拡大、さらに価値観の多様化が進む中で、「本当に時間を割けない」「無理に参加するのは負担が大きすぎる」と感じる人が増えています。育児や仕事で精いっぱいの生活の中で、役員の当番や集まりが重荷となり、「やめたい」「入らない」という声が少しずつ表に出るようになりました。
インターネットや書籍を通じて「PTAは任意参加である」という情報が広がったことも大きな転機です。「本当は強制ではない」という事実を知り、勇気を持って参加を拒否する人が出てきました。社会全体の意識が少しずつ変わり始めている今こそ、あらためて「PTA活動を拒否する方法」や「拒否したらどうなるのか」を具体的に考えてみることが必要です。今回はその最もシンプルな方法と注意点を紹介していきます。