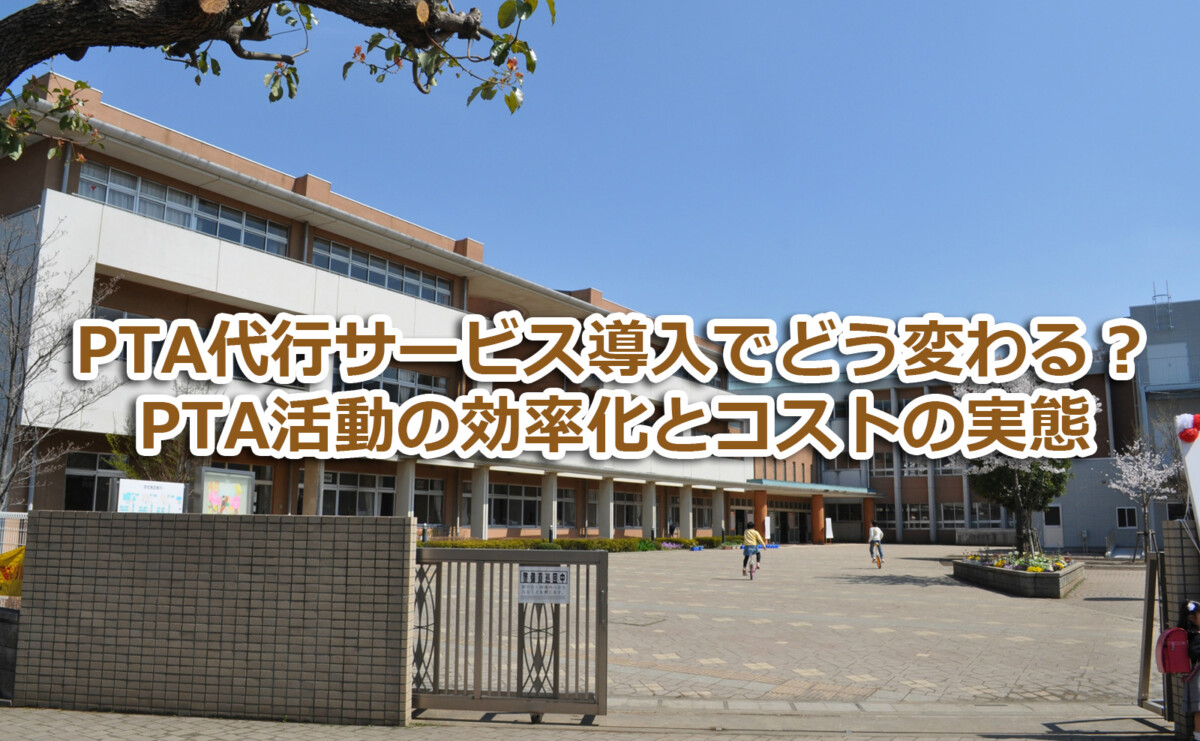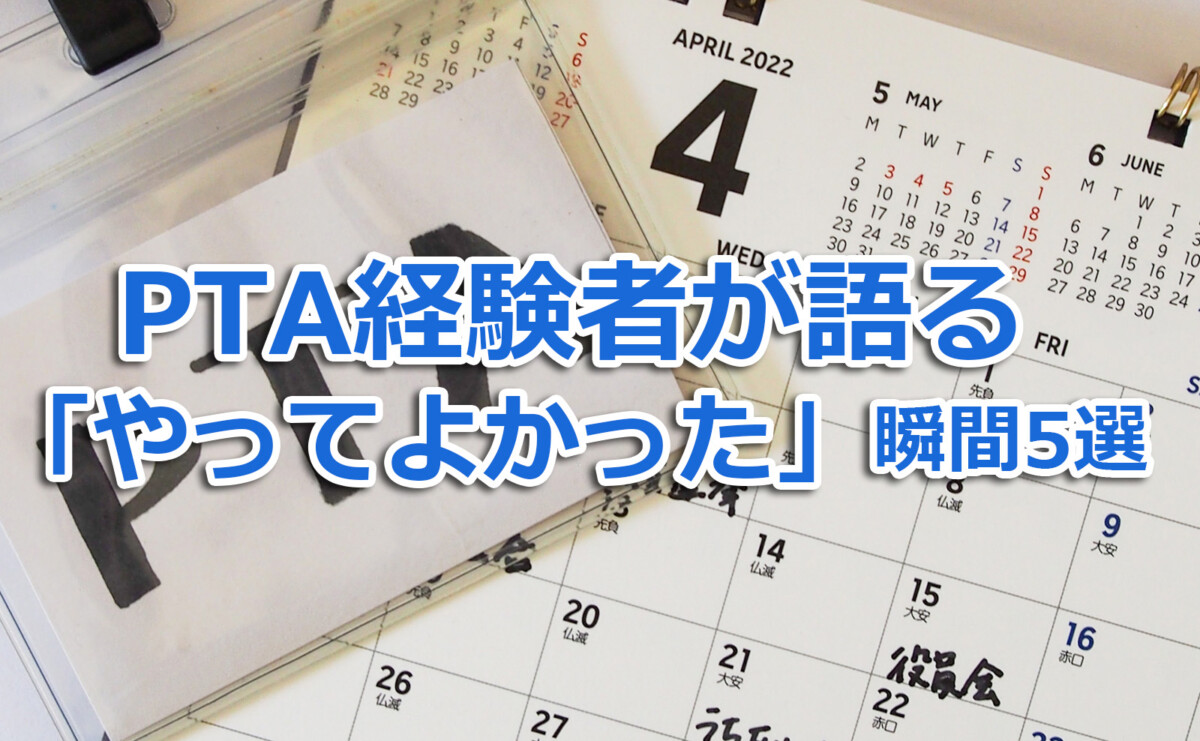PTA会長をどうやって決めるか。これは毎年多くの学校で繰り返される、頭の痛いテーマです。役員の中でも特に責任が大きく、時間や労力の負担も重い立場であるため、「自分からやりたい」と立候補する人は決して多くありません。その一方で、誰かが担わなければ活動は回らないため、結果的に「押し付け合い」になってしまったり、「仕方なく引き受ける」人が出たりするのが現実です。
私自身もその一人でした。シングルファーザーとして子育てをしているなかで、何となくPTA役員を引き受けることになり、気づけば6年間続け、そのうちの2年間は会長を務めました。男親であることや自営業だったこともあってか、周囲からは「PTA会長をやってくれませんか?」と半ば当然のように頼まれ、断り切れずに引き受けたのです。こうした経緯からもわかるように、PTA会長の選出には不透明な部分や、個人の事情が十分に考慮されない現実があります。
公平さを重んじて「くじ引き」で決める学校もありますが、事情を抱えた人に当たってしまったり、やりたくない人が引き当ててしまったりすると不満が残ります。推薦制にしても裏での根回しや断りづらさが課題になり、輪番制なら順番が来た人の負担感が大きいなど、それぞれに短所があるのです。
そこで今回は、代表的な会長選出のパターンを整理し、それぞれのメリットとデメリットを解説します。そのうえで、学校や地域の事情に合わせた柔軟な運用方法や、参加者全員が納得しやすい公平な仕組みづくりのヒントを紹介していきます。