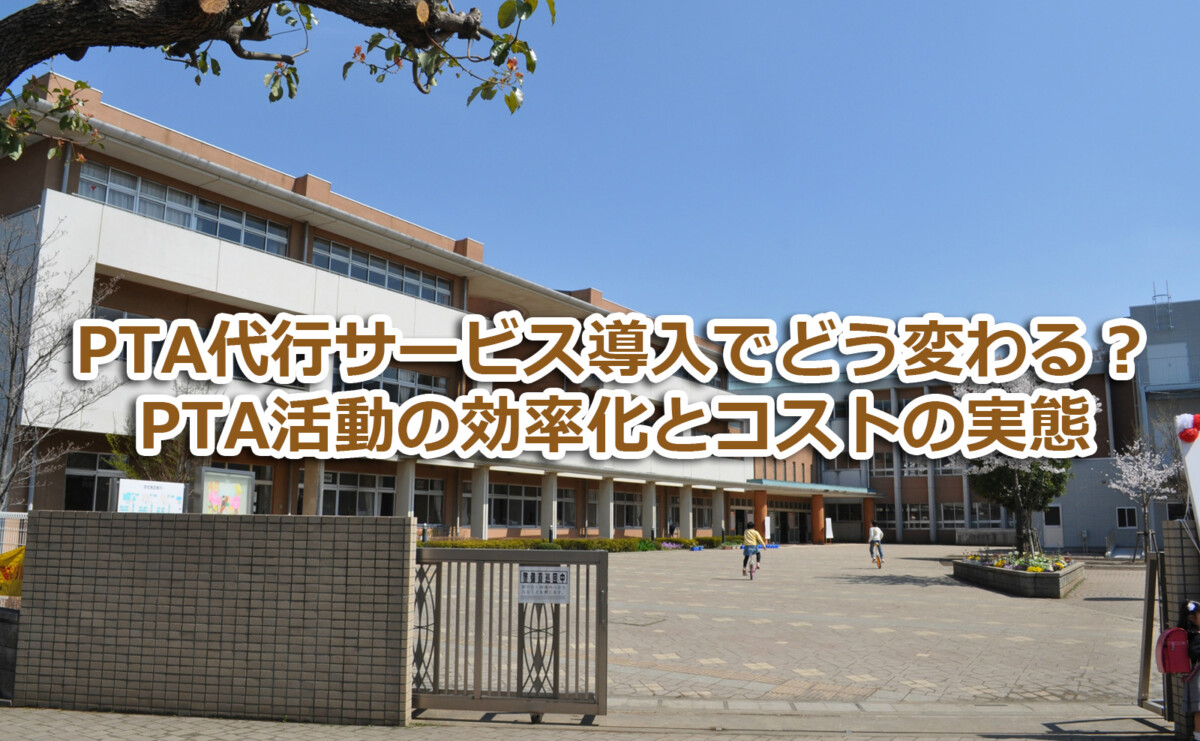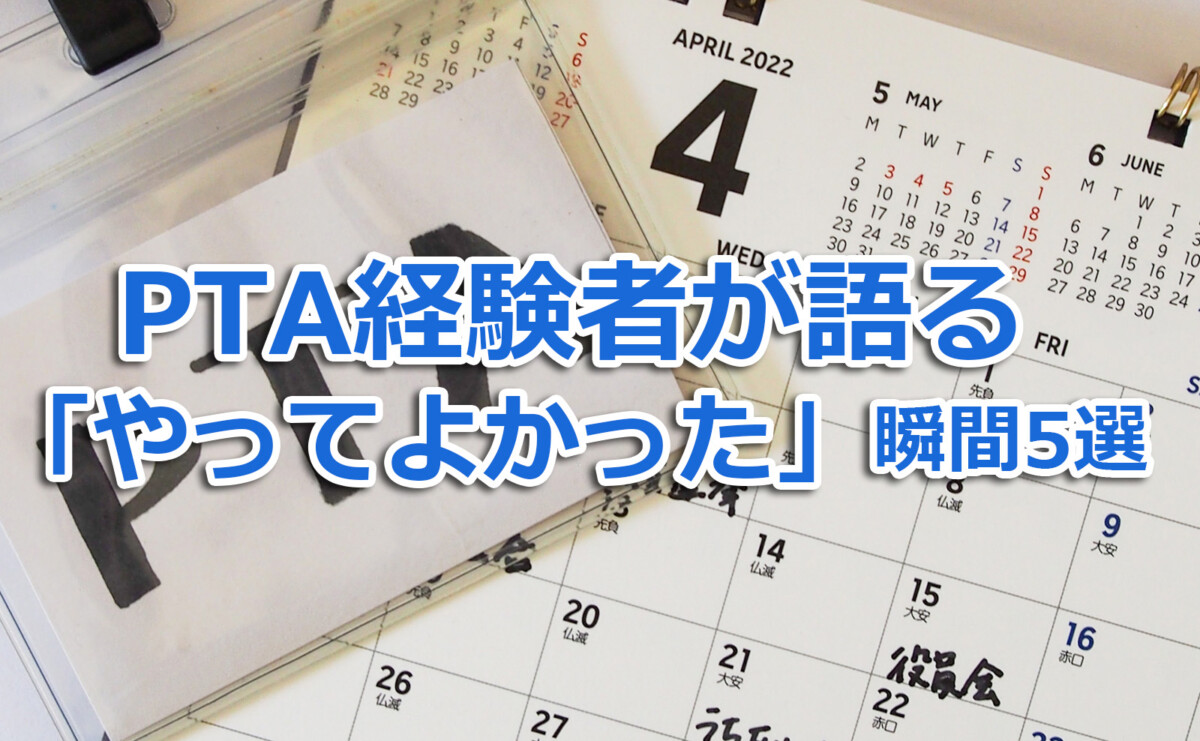PTA役員による「路駐パトロール」の現場
学校行事の日に駐車場問題が発生すると、その矢面に立たされるのがPTA役員です。運動会や学芸会では、事前に「車での来校禁止」「近隣施設への駐車厳禁」と周知しても、実際には違反がなくならないため、当日はPTA役員が交代で校門や周辺道路に立ち「路駐パトロール」を行うことが一般化しています。これは、単なる見回りではなく、違反している車の保護者に直接声をかける必要があり、心理的にも大きな負担を伴う活動です。
実際の現場では「なぜここに止めてはいけないんだ」「後で買い物するからいいだろ」「じゃあどこに止めればいいんだ」といった反発が頻発します。時には強い口調で詰め寄られたり、逆に無視されて立ち去られたりすることもあります。役員は同じ保護者同士であるため、相手との関係性を気にして強く言えず、結果的にストレスを抱え込むことが多いのです。「注意する側」と「注意される側」という立場の違いが、保護者同士の関係をぎくしゃくさせる要因にもなります。
さらに、周辺住民や店舗から直接苦情を受けるのもPTA役員の役目です。「自宅前に停められて迷惑だ」「お客さんが駐車できず困っている」などの声を受け止めつつ、すぐに対応しなければなりません。地域の代表のような役割を果たす一方で、正式な権限があるわけではないため、解決策を持ち合わせていないというジレンマも抱えています。
このように、PTAによる路駐パトロールは「学校や地域のために必要」と理解されつつも、その負担は大きく、役員にとっては精神的にも肉体的にも過酷な活動です。本来なら子どもの活躍を安心して見守りたいはずの一日が、パトロールに追われる日になってしまう現状は、今後の在り方を考える上で大きな課題だといえるでしょう。
- 学校行事ではPTA役員が「路駐パトロール」を担う
- 保護者からの反発や無視などで精神的負担が大きい
- 周辺住民・店舗からの苦情対応も役員の役目になる
- 子どもを見守るよりトラブル対応に追われる実態
様々な地域や学校での工夫・対策
駐車禁止の徹底周知
学校によっては行事前に配布するプリントや、学校ホームページ、メール配信、SNSなどを活用し「駐車禁止」「近隣施設への駐車厳禁」を強く呼びかけています。単なる注意書きではなく、迷惑駐車が地域トラブルにつながった具体事例を紹介することで、保護者に当事者意識を持たせる工夫もあります。繰り返しの周知は徹底に欠かせません。
公共交通機関や自転車利用の推奨
多くの学校では「徒歩または自転車での来校」を基本とし、公共交通機関の利用を促す方針を打ち出しています。バスや電車の時刻表を一緒に配布したり、自転車置き場を臨時に拡張するなど、代替手段を具体的に提示することが大切です。「どう来ればいいのか」を示すことで保護者の行動を後押しできます。
臨時駐車場の確保
地域によっては近隣の公園や企業、公共施設の駐車場を一時的に借り、来場者用に解放する取り組みもあります。台数に限りはありますが、徒歩数分の距離に臨時駐車場を設けるだけでも無断駐車の抑制につながります。さらに、混雑が予想される場合はシャトルバスを運行し、安全と効率を確保する工夫も見られます。
学校・自治体による見守りスタッフ配置
PTAだけに負担をかけないよう、学校職員や自治体が協力して見守りを行う事例も増えています。特に地域安全パトロールや交通指導員の協力を得ることで、役員の心理的負担を軽減できます。保護者が「注意する側」と「される側」に分かれる構図を避けることができ、トラブル防止に効果的です。
「住民・保護者が協力する文化」の啓発
駐車問題を根本的に解決するには「自分一人くらい大丈夫」という意識を変える必要があります。学校や地域が協力して、子どもたちの行事を守るためにルールを守ることの大切さを繰り返し発信し、保護者同士が声を掛け合える雰囲気をつくることが大切です。地域ぐるみで協力する文化が育つことで、自然と迷惑駐車も減っていきます。