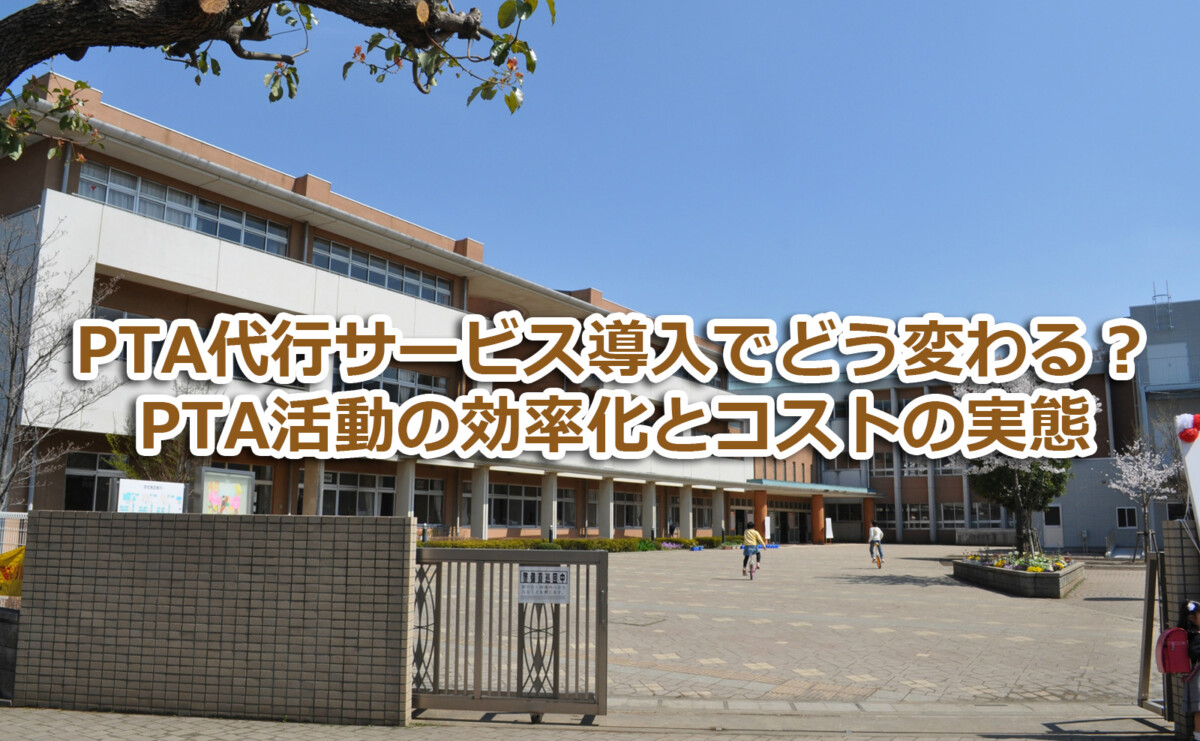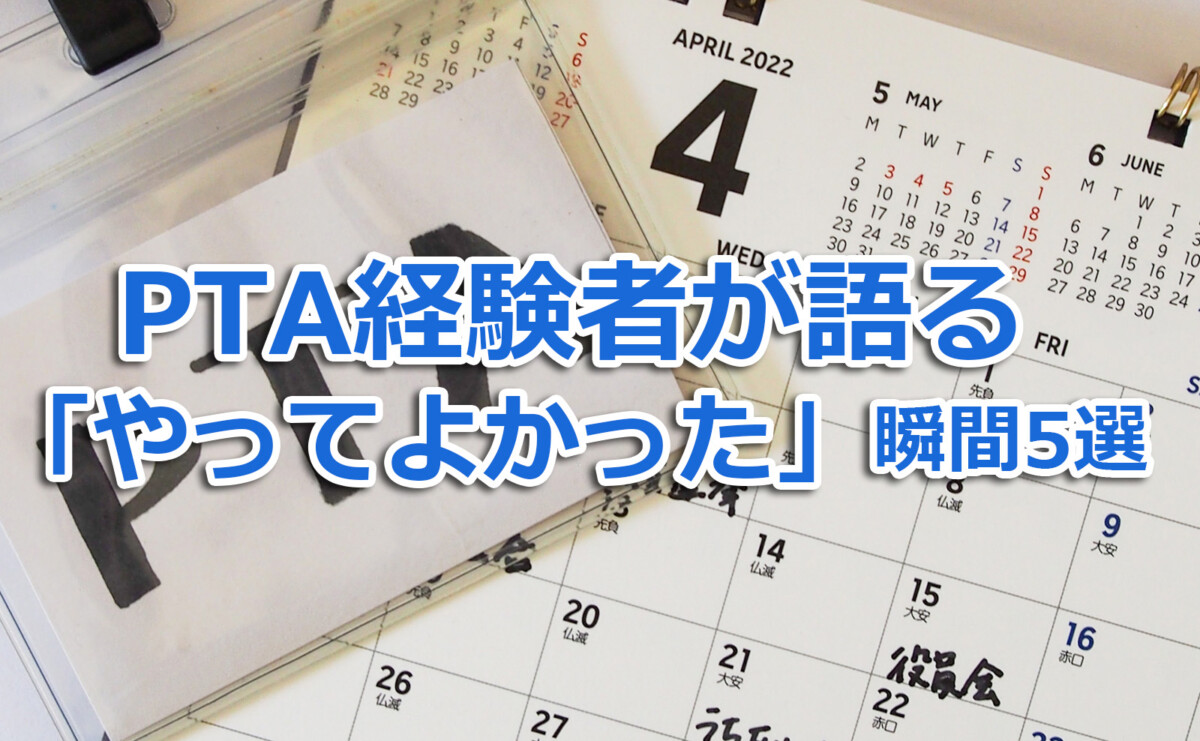納得感を高める委員決めの工夫
立候補制・推薦制・くじ引き制のメリット・デメリット
委員決めの方法として多くの学校で用いられるのが、立候補制・推薦制・くじ引き制の3つです。立候補制は「自ら希望する人が引き受けるためモチベーションが高い」という利点がありますが、人気のない委員は人が集まらず偏りが生じやすいという課題があります。
推薦制は「周囲が適任と考える人を選べる」という良さがある一方で、「押し付けられた」と感じる人が出やすく、人間関係に亀裂が生まれるリスクがあります。
そして、くじ引き制は「公平性が高い」という点で評価されますが、事情のある人まで当たってしまうと不満が募りやすいのが難点です。
つまり、どの方法にも一長一短があり、学校や地域の事情に応じて使い分ける必要があります。大切なのは「この方法で決める」というルールを事前に明確にし、全員が納得して臨めるようにすることです。
「やれる人がやれる範囲で」を前提にした柔軟な体制
納得感を高めるためには、「できる人にできることをお願いする」という柔軟な発想が欠かせません。これまでのPTA活動は「必ず全員が平等に負担する」という考え方が強く、事情のある家庭にとっては大きな負担となっていました。
しかし、現代は共働きやひとり親世帯も多く、従来の一律な役割分担は現実的ではありません。そこで、「フルで関わるのは難しいが、一部の作業なら手伝える」「イベント当日のみ参加可能」といった多様な関わり方を認める仕組みが求められます。
役員の中でも主担当とサポート担当を分けることで、負担が集中するのを防げます。全員が同じ量の負担を担うのではなく、状況に応じた役割を調整することが、結果として不満を減らし、納得感を高めるポイントとなるのです。
複数人制・任期短縮・分担制などの代替策
「委員になったら1年間フルで活動」という従来のスタイルに縛られると、保護者の負担は大きくなりがちです。そこで有効なのが、複数人制や任期短縮、分担制といった代替策です。
例えば会長職を2人で担当する「ツイン制」にすれば、一人にかかる責任や時間を軽減できます。任期を1年から半年に短縮する方法もあり、「長期的に縛られるのは難しい」という保護者にとって参加しやすい環境をつくれます。さらに、会計や広報などの役割を細分化し、業務を小さなタスクに分けて複数人で分担する仕組みも効果的です。
こうした工夫により「一人が背負い込まない体制」を整えることで、役職に就いた人の心理的負担が和らぎます。役割の柔軟化は、トラブルを減らすだけでなく「参加してよかった」というポジティブな経験につながりやすいのです。